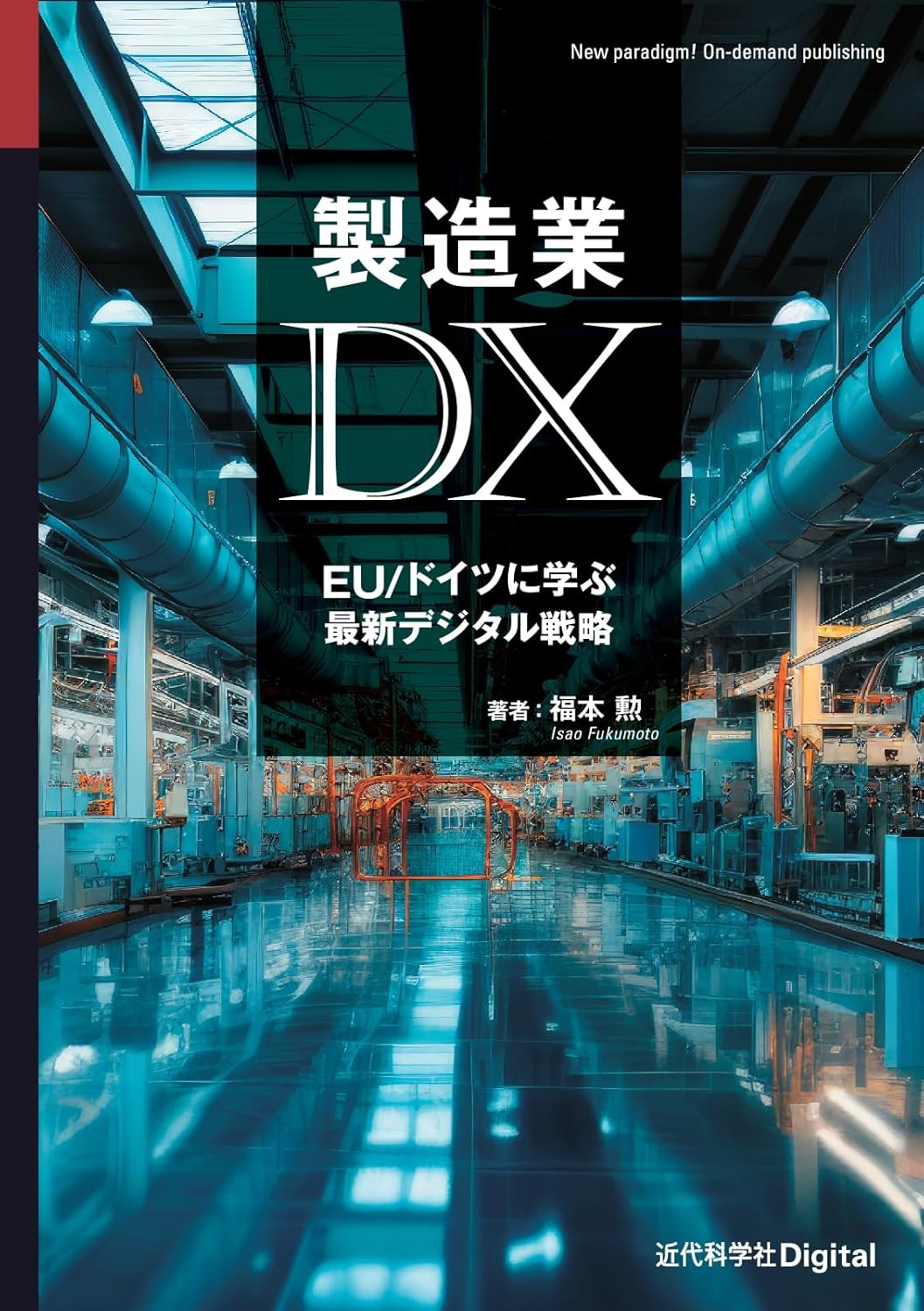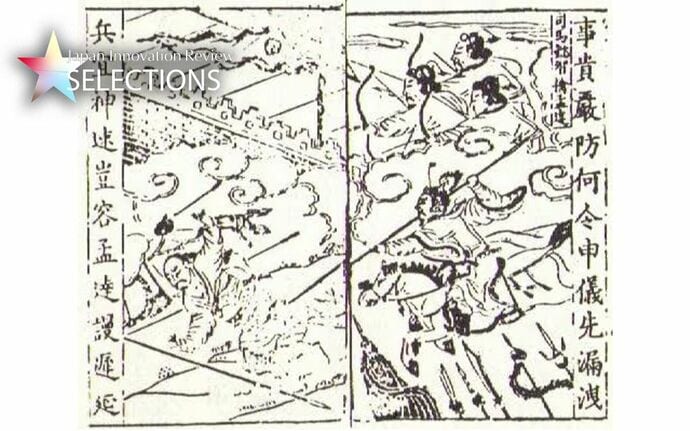出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
日本の製造業におけるDXの必要性が叫ばれて久しい。しかしながら、DXに取り組み、成果を出せている企業は少ない。何がDXの進展を阻んでいるのだろうか──。その要因の1つとして「日本の製造業は業務改善に偏重し、部分最適に終始する傾向がある」ことを挙げるのは、企業のデジタル化を支援するアルファコンパス 代表CEOの福本勲氏だ。2023年12月、書籍『製造業DX EUドイツに学ぶ最新デジタル戦略』(近代科学社Digital)を出版した福本氏に、製造業のDXを成功に導くためのヒントや、世界の先進工場「ライトハウス」に選定された企業の特徴について聞いた。
DX成功のかぎは「経営者自らが未来視点を持てるかどうか」
──著書『製造業DX EUドイツに学ぶ最新デジタル戦略』では、日本の製造業においてDXがなかなか進まない状況を指摘しています。そこにはどのような要因があると捉えていますか。
福本勲氏(以下敬称略) 3つの要因があると考えています。第1の要因は、ITやデジタル技術の導入自体が目的化していることです。本来、デジタルはあくまでも手段であり、企業の将来像を実現するために活用すべきものです。しかし、多くの企業が「DX=ツール導入」と短絡的に捉えてしまっています。
第2の要因は、多くの製造業の現場ではIT人材が不足しており、ITベンダーへの過度な依存が生じていることです。このような体制では自社主導での変革は難しく、業務の本質的な見直しや競争力の強化につながりにくくなります。
第3の要因は、DXへの取り組みが既存ビジネスの効率化にとどまり、部分的な業務改善に終始していることです。「現状をいかに改善するか」という視点に偏っていると、新たな価値の創出やビジネスモデルの転換といった本質的な変革には踏み込めません。
この3つのうち、特に大きな壁となっているのが第1の要因である「IT・デジタル導入の目的化」です。DXとは、自社の存在意義を見直し、将来のあるべき姿を描いた上で、その実現に向けた戦略と手段を築く取り組みであるべきです。
「日本企業にはデジタルケイパビリティ(デジタル活用に求められる組織能力)が不足している」との指摘もありますが、その背景には、DXの推進を現場任せにする企業風土があるように思います。経営者自らが未来視点を持ち、「5年後、10年後に自社はどうあるべきか」というビジョンを描いた上で、主体的に変革を推進していく姿勢こそが重要です。