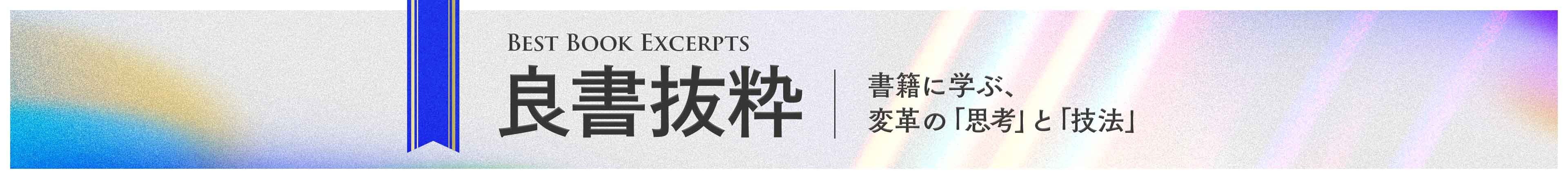写真提供:©Budrul Chukrut/SOPA Images via ZUMA Press Wire/日刊工業新聞/共同通信イメージズ
写真提供:©Budrul Chukrut/SOPA Images via ZUMA Press Wire/日刊工業新聞/共同通信イメージズ
トランプ政権の不透明な関税策、ロシアによるウクライナ侵攻、米国による対中半導体規制、台湾有事リスク、欧州の気候変動規制──。地政学・経済安全保障に関するリスクが拡大・深刻化する中、企業の事業活動が危ぶまれるケースが年々増えている。こうしたリスクによるビジネスへの悪影響を最小限に抑えるべく、企業はどのように向き合い、備えるべきか。本稿では『ビジネスと地政学・経済安全保障』(羽生田慶介著/日経BP)から内容の一部を抜粋・再編集。国家間の政治力がぶつかり合う現代の国際経済社会において、ビジネスパーソンが押さえておくべき地政学・経済安全保障リスクと対応策を考える。
地政学リスクや経済安保上の緊張が高まる中、インフラ企業や半導体、情報通信、航空宇宙分野の団体・組織が、国家によるサイバー攻撃の標的として狙われやすくなっている。生成AIで高度化するサイバー攻撃に、企業はどう対処すべきか。
※本記事は、2025年1月時点の情報に基づいています。
10大リスク_サイバーリスクの高度化
脅威が増すサイバー攻撃
ここ数年で企業・組織が受けたサイバー攻撃の件数や被害金額は世界的に急増している。
グローバルにハッカー対策サービスを展開するサイバーセキュリティークラウドによれば、同社が検知したWebアプリケーションへのサイバー攻撃は2023年の1年間で7億回を超えた。1秒間に23回のサイバー攻撃を受けた計算になる。
サイバー攻撃は今や、いかなる企業にとっても他人事ではない。米連邦捜査局(FBI)インターネット犯罪苦情センターには、2023年には約88万件の届け出があり、その被害額は125億ドルに達している(次ページ図表5・6)。
特に基幹インフラを担う企業がサイバー攻撃を受け、事業の停止に至った場合の影響は大きく、国民生活を脅かす経済安保上のリスクとなる。
2023年7月に名古屋港コンテナターミナルのシステムがロシアを拠点とするハッカー集団のサイバー攻撃を受け、約3日間にわたって同ターミナルからのコンテナの搬入・搬出が停止した。この件は、経済安全保障推進法上の「特定社会基盤事業」に「一般港湾運送事業」を追加する契機となった。
また、近年はサイバー空間が地政学上の争いの場となり、企業が直接的に地政学的な緊張関係の影響を被りやすくなっている。国家が関与したサイバー攻撃によって、敵対国の重要インフラの機能を停止させたり、重要技術や個人情報を窃取したりすることが増えている。