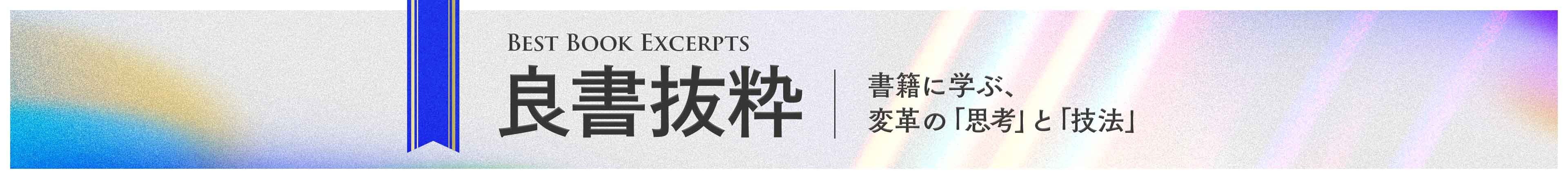写真提供:共同通信社
写真提供:共同通信社
「失敗は成功の母」とは言われるものの、実際には、失敗の危険性の高いことに挑むのは勇気がいる。特に減点主義が蔓延している日本企業では、あえてリスクを冒さない“無難”志向が強く、それがイノベーションを阻害する要因とも指摘される。そうした中、グローバルで成功している優良企業の事例を交えながら、失敗を類型化し、失敗を通じて生産性を向上させるためのフレームワークを提供しているのが、『失敗できる組織』(エイミー・C・エドモンドソン著、土方奈美訳/早川書房)だ。同書の内容の一部を抜粋・再編集し、そのポイントを紹介する。
「ひょっとしたら大丈夫かもしれないが、悪い予感がする」。誤警報への叱責を恐れることなく、現場の人間が安心して発言できる環境は、どうすれば構築できるか。トヨタ自動車の事例から考える。
誤警報を歓迎する
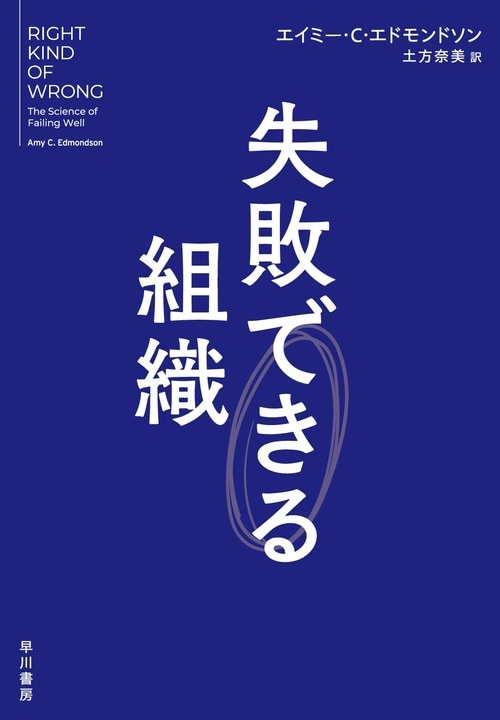 『失敗できる組織』(早川書房)
『失敗できる組織』(早川書房)
どうすれば複雑な失敗が起こる前に察知できるだろうか。
多数の要因が過去に例のない特異なかたちで絡み合って生じるという複雑な失敗の性質を考えると、そんな試み自体が無駄に思える。だが実際にはシンプルで洗練されたやり方がある。それは誤警報に対する考え方を改めるところから始まる。
トヨタ自動車の工場ではミスが本格的な失敗に発展する前に作業員がアンドンを引いてチームリーダーに知らせる仕組みがあるというエピソードを思い出してほしい。
チームリーダーとメンバーは潜在的問題を大小にかかわらず調査し、問題を解決するか、脅威はなかったものと判断する。アンドンが引かれて生産ラインが停止したケースが12回あったとしよう。そのうち実際に問題があったのが1回だけだったとしたら、会社は残りの11回の誤警報についてスーパーバイザーの時間を無駄にしたといって怒るだろうか?
まさにその逆である。本当のミスではなくアンドンが引かれた場合、それは有益な訓練とみなされる。誤警報は貴重な学習の機会、どんなミスが起こりうるか、それを減らすために何ができるかを学ぶ場とみなされる。これは企業文化の話ではない。実用的アプローチだ。アンドンが引かれるたびに長い目でみれば時間を節約し、品質を高める機会が生まれる。
同じようなアプローチが医療現場でも使われている。緊急対応チーム(RRT)と呼ばれるイノベーションだ。病室の看護師が患者のちょっとした変化(顔色が悪い、具合が悪そうだ)に気づいたとする。それは心臓発作のような差し迫った危険の表れかもしれないし、そうではないかもしれない。