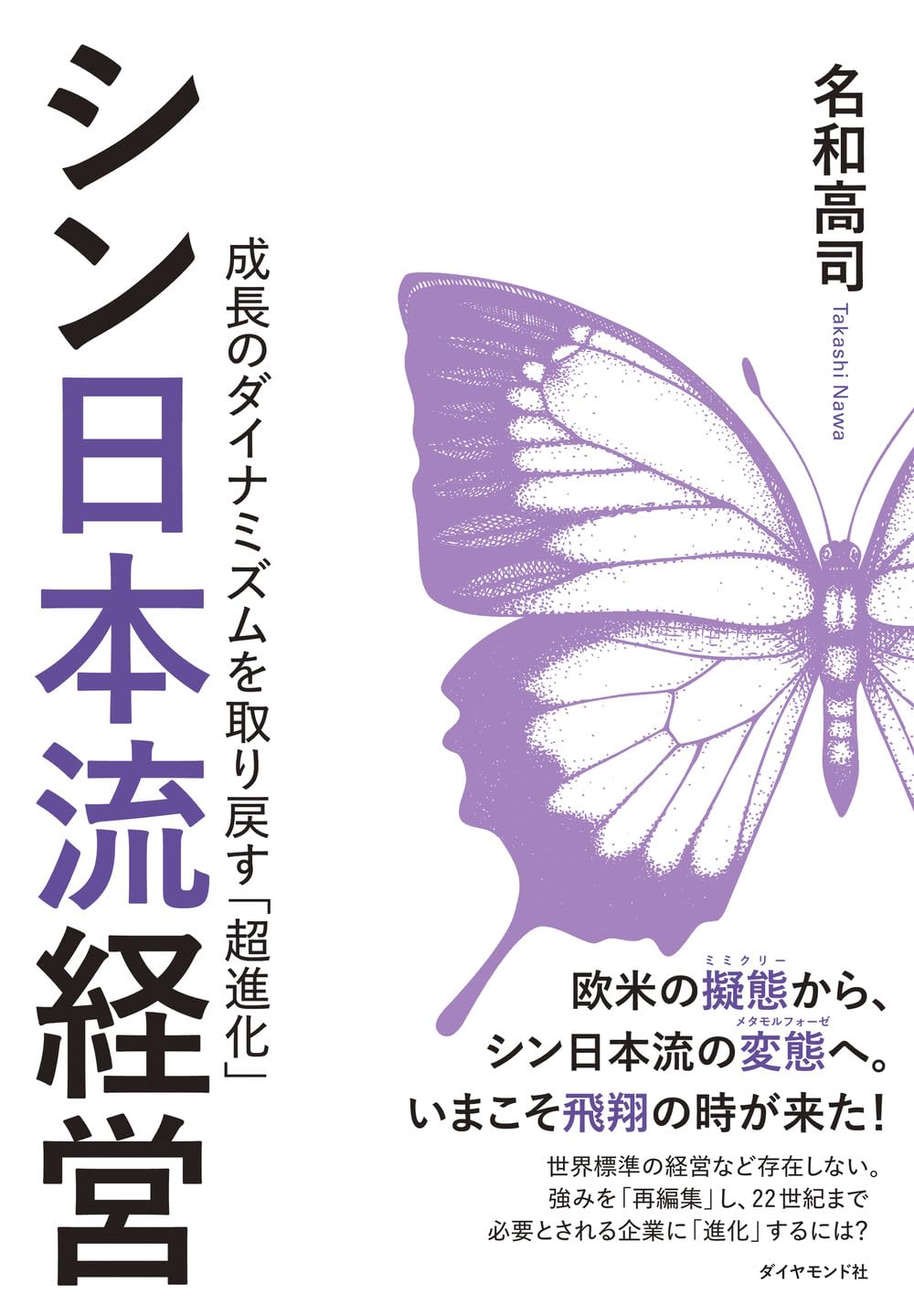出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
バブル崩壊以降、日本企業はそれまでの日本流から「世界標準」の経営スタイルに舵を切り、現在も世界最先端の経営モデルを追いかけ続けている。しかし、こうした意思決定は「日本流の現場の強みを軽視しており、迷走を招きかねない」と警鐘を鳴らすのが、2025年2月、書籍『シン日本流経営――成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」』(ダイヤモンド社)を出版した、京都先端科学大学教授・一橋ビジネススクール客員教授の名和高司氏だ。成長を続ける国々の企業が独自の経営モデルに磨きをかける中、日本企業は何をよりどころに経営をアップデートすべきなのか、同氏に話を聞いた。
日本企業が目指すべき第三の道「異成長」
──著書『シン日本流経営――成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」』の序章では、日本に開かれた「3つの道」として、第一の道「超成長」、第二の道「脱成長」、そして第三の道「異成長」について解説しています。それぞれどのような概念なのでしょうか。
名和高司氏(以下敬称略) 第一の道である「超成長」とは、指数関数的な成長を目指すものです。超成長モデルの代表的な企業には、マグニフィセント・セブンと呼ばれるテック企業7社(グーグル=現アルファベット、アップル、フェイスブック=現メタ、アマゾン、マイクロソフト)があり、いずれも近年爆発的な成長を遂げています。
日本企業にも一握りですが、超成長を実現した企業は存在します。「失われた30年」の中においても異次元の成長を遂げてきたニデック(旧日本電産)、ファーストリテイリング、ソフトバンク、リクルート、キーエンス、ダイキン工業などです。
第二の道である「脱成長」とは、成長志向にとらわれない考え方です。定常型社会や幸福主義、脱成長コミュニズムなど、様々な論調が存在しますが、いずれも脱成長と表現できます。しかしながら歴史をひもとくと、脱成長主義が目指す世界観は、たとえ実現したとしてもごく短命に終わることが分かっています。
第三の道である「異成長」は、いずれにも当てはまらないものです。そもそも「成長するか・しないか(脱成長)」という問いは一次元の話です。従来の「量的な成長」「スピード的な成長」といった測りやすいものではなく、「違う次元の成長をつくる」という考え方が異成長の特徴です。
言い換えるならば、「軸をずらす」ことです。軸をずらすことによって、新たなイノベーションを生み出すことができます。そして、今まさに日本に求められているのが、この異成長の考え方といえます。